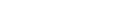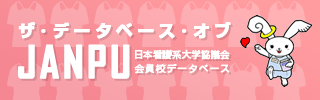- 香川大学医学部看護学科 地域精神看護学講座(在宅看護学)
- 林 信平
岡山大学医学部保健学科看護学専攻を卒業後、同大学院を修了。大学病院での臨床経験を積んだ後、川崎医療福祉大学や日本赤十字広島看護大学で基礎看護学の教育に携わる。現在は、香川大学博士後期課程に在籍しながら、現職に従事している。
これから看護を学ぶ人へ
【看護師としての歩み】
看護師になって20年以上が経ちました。振り返ると、長い道のりでした。学生のころの私は、まさかJANPUで自己紹介記事を書く日が来るとは思いもしなかったでしょう。
私はこれまで、手術室・病棟・ICUで9年間勤務し、その後、基礎看護学と在宅看護学の教員として約12年間、教育に携わってきました。職場や業務内容が変化する中で、新たな挑戦を続けることはとても楽しいものです。未知の世界に飛び込む際に、「なんとかなる」と思える無根拠な自信こそが、私の原動力だったのかもしれません。
もちろん、数多くの失敗も経験しました。しかし、振り返ると、失敗から学べることのほうが多かったと感じています。論語には「過ちて改めざる、是を過ちという(過ちを犯しても、それを改めないことこそが本当の誤りである)」とあります。失敗を恐れず、それを糧に成長していきたいと思っています。
【学生の皆さんへ——「準備の大切さ」】
私が学生に伝えていることの一つに、「準備の大切さ」があります。臨床の現場では、想定外のことが多々起こります。しかし、事前にできる限りの準備をしておくことで、対応力が大きく変わります。
特に診療補助業務では、「医師がやるから」と受け身にならず、自分が実施するつもりで物品の準備や手順を考えておくことが重要です。その意識があると、実際の現場でもスムーズに動けるようになります。臨床に出る前に、「準備がどれほど重要なのか」を意識し、実践してほしいと思います。
【地域での研究と活動】
香川大学に来て6年目になります。現在、私は社会的つながりの希薄化が健康に及ぼす影響について研究しながら、地域づくりに参画しています。地域の人々と直接関わることで、その活動の楽しさややりがいについて、より深い知見を得ることができました。
看護学における臨床研究は、現場との連携が欠かせません。研究協力をいただいた方々に、何らかの形で還元できるよう進めることが肝要です。単にデータを収集するだけでなく、地域とともに研究を進めていくことが重要だと考えています。現在は、社会的孤立とフレイルの関係性について調査研究を行っています。
【これから看護を学ぶ方へ】
看護学は、病者だけを対象とする学問ではありません。全年齢のあらゆる健康状態の人を対象とし、看護と無関係に存在する人はいません。
人は皆、個別性があり、考え方もさまざまです。時には、理解しがたい複雑な状況に直面することもあるでしょう。そんなときこそ、以下の力が求められます。
<人間力>対象者の置かれた状況に寄り添う力
<論理力・判断力>知識を活かして考え、適切な判断を下す力
<技術・行動力>正確な技術を持ち、実践できる力
<体力>ハードな勤務を支える力
<協調性>他者と協力して動く力
これほど多くの能力を必要とする仕事は、なかなかありません。だからこそ、看護は終わりのない学びの場でもあります。自身の力を磨き続けることで、より良い看護を提供できるのです。
【教育と研究の道】
看護を学ぶ中で、教育や研究の道を選ぶこともできます。自身の実践から紡がれた言葉は、学生にとって響きやすいものです。研究においても、臨床で感じた疑問や未解決の問題に取り組むこと、時間を忘れて没頭すること、同僚と意見を交換すること、学会で初対面の先生と議論すること——すべてが楽しく、学びのある経験です。
私自身も、これらの経験をもとに教育や研究に携わっています。
これから看護を学ぶ皆さんが、自らの可能性を広げながら、より良い未来を築いていくことを願っています。